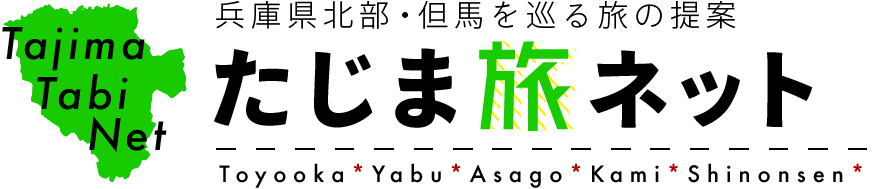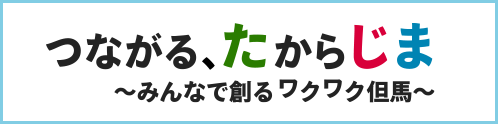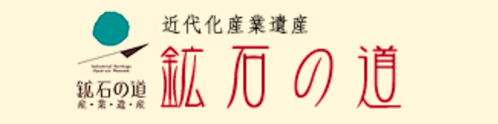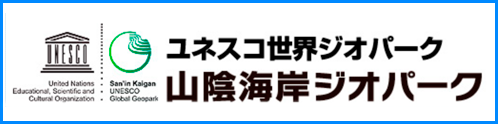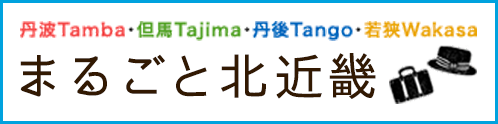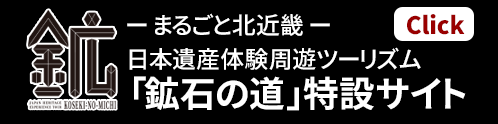豊岡観光協会のフェースブックものぞいてみてください。豊岡の話題や、最新情報などを、随時更新してお知らせしています。
豊岡の「まちなか縁日」、 まだまだ続きますよ。「豊岡のまちなか」の普段気づかないところを、夕涼みを兼ねて「ぶらり散策」はいかがでしょうか。
7月1日は、豊岡市城南町(小尾崎区)の「鳩場(はとば)地蔵」さんの縁日です。
「小尾崎」と隣の「豊田」との境には、かってご城下と町屋を分ける番屋があり、近くに船着き場があったそうです。
小尾崎の「鳩場地蔵」さんは「波止場地蔵」とも呼ばれ、かっての船着き場の名残ともいわれます。
「慶応年間」にお札の版木を新調した時には「鳩場地蔵」といっていたようです。版木の下、台座のところに「豊岡鳩場」と書いてあります。




引き続き、3日には中央町の来迎寺で「毘沙門天王大祭」、6日は山王町「日吉神社」の「祇園大祭」、7日は中央町の「自性院」の「豊岡薬師大祭」、元町の「幸之神神社大祭」」と続きます。


来迎寺の「毘沙門堂」

鐘楼の下には、NHK大河ドラマの「黒田官兵衛」の時代、播磨征伐、但馬征伐、鳥取征伐と続く戦国時代、豊臣秀吉が但馬を平定した後、この地「豊岡城」を治めた「宮部善祥房継潤(ぜんしょうぼうけいじゅん)」(のちの鳥取城主)の顕彰碑や、本堂前にある「杉原伯耆守長房」の墓碑、蕪村と並ぶ江戸時代の俳人「蝶夢翁」の顕彰碑も訪ねてみてください。

豊岡城主「杉原長房」の墓碑

「蝶夢翁」の顕彰碑






14日は「青空市場」にある「木守地蔵・あかり地蔵」、15日は豊岡藩主、京極家とゆかりのある「立正寺」の「妙見宮夏祭」とのお祭りです。


「木守地蔵」はもともと神武山の山麓にあったものですが、戦後になって京極家から譲り受け、地元の生田東区が管理してお祀りしています。


妙見宮前にある「京極杞陽(きよう)」の句碑

本堂の屋根には、京極家の「家紋」の瓦があります。
「豊岡まちなかの縁日」は、古くから続くもの、「豊岡城下町」の形成の時代から守られてきたものなど、当時の庶民の信仰と娯楽をしのぶことができます。
25日には、豊岡市京町(本区)の「豊岡稲荷(本町稲荷)神社」の「天神祭」があります。
「ご城下のお稲荷さん」として豊岡京極藩の庇護を受けていましたが、いまでは地元の地区でお世話をされています。城下町絵図のお城の下、ちっちゃな池の近くにあるのがわかるでしょうか。




「城下町出石」、「コウノトリの郷公園」、「玄武洞」など近くの見どころを訪ねるついでに、豊岡駅近くのビジネスホテルに泊まって、ふだんは気づかない「豊岡まちなか」を、夕涼みがてら散策してみてはいかがでしょう。