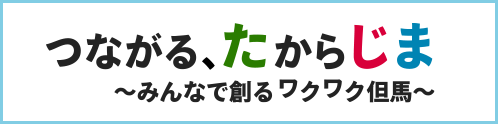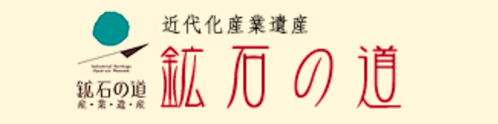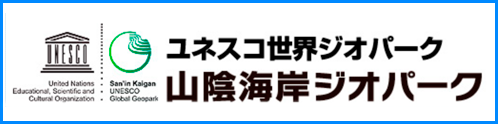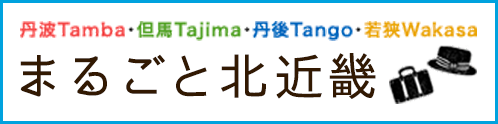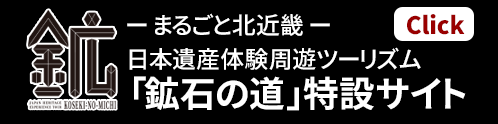豊岡観光協会のフェースブックものぞいてみてください。豊岡の話題や、最新情報などを、随時更新してお知らせしています。
5月の薫風を受けて、「まちなかぶらあるき」はいかがでしょうか。
寿公園は、碁盤の目に整理された市街地の道路のなかに、パリの凱旋門のある「エトワール広場」(シャルル・ド・ゴール広場)を思わせるちょっと異質なロータリーになっています。
その中心部に、椅子に座って豊岡市内をいつくしむように見つめる「中江種造翁」の銅像があります。
「中江種造」さんは大正の末に豊岡のまちに上水道を敷設するときに多大の私財寄付をしました。
この功績に感謝して5月11日には毎年「水道祭」が開催されていますが、今年は「新型コロナ感染拡大防止」のため規模を縮小することがあります。

ここの交差点は、明治期からの「円山川の河川改修」と「大豊岡構想」による区画整理事業で移転した地区の要望により、小田井神社から豊岡駅に至る路線が設けられ、この路線が十字路と交わる六差路となっています。

車のスムーズな交通を確保するため、めずらしい「ラウンドアバウト方式」の環状交差点になっています。今では国道の経路が変わってしまいましたが、かって国道がこのような方式になっていたのは、全国でも珍しいとのことです。
地元では「寿ロータリー」とか親しみを込めて「どうぞうさん」と呼んでいますが、初めて通った人は、ときどき抜け出る方向が分からなくなってしまうことがあるようです。
豊岡では、大正時代からすでにこの方式で車の交通整理をしていたことになります。「豊岡1925」のフロア中央は、このロータリーをイメージしたデザインになっています。

豊岡の市街地は、従来の円山川沿い中心の町並みから、明治から大正にかけて鉄道敷設、円山川大改修など大事業が続き、明治42年に開業した豊岡駅を中心にした町づくりへと大きな区画整理が行われていました。
「関東大震災」の2年後、大正14年に起きた「北但大震災」で隣の城崎町を含め、市街地の大半が焼失する大きな被害を受けました。
当時の写真です。右端が「豊岡駅」です。中央に「ロータリー」が見えます。

5月23日は、その「震災記念日」で、市内各地でこれに併せた防災訓練などが実施されます。
各方面からの支援と励まし、そしてみんなの努力の結果、現在の復興を成し遂げましたが、東日本大震災などの大災害の早期復興を願う気持ちが豊岡市民に人一倍強いのも、こうした経験があるからでしょうか。
豊岡市街地には、豊岡市役所旧庁舎をはじめ、ところどころに防災を意識した当時の復興建築が残っています。
改装して診療所とギャラリーとして復活した「旧但馬労働監督署(但馬合同銀行支店)」

壁面を銅版で覆った「うろこの家」のような外観。現在は無人の倉庫です。

3軒の商店が連なった外壁。アーケードにかくれて気づきにくいですが、周辺には同じような復興の面影を残す外観のお店がほかにもあります。





外観のデザインにも、いろいろな工夫が見られます。
「旧山陰合同銀行(当時兵庫県農工銀行)」(現在は「豊岡1925」として新たな歴史がスタート)。
昭和9年建設、有名な建築家「渡辺 節」の設計。国登録有形文化財に指定されています。

新豊岡市庁舎建設にあたり、曳家によって約25メートル道路側に移設された「旧豊岡町役場」は、「稽古堂」として生まれ変わりました。昭和3年の建築で、設計は「原科準平」です。





レンタサイクルも利用できます。
「カバンストリート」にあるじばさんショップ「とよぶら」には、ミシュラン自転車を4台置いています。

町なかには、このほかに「豊岡城下町の面影」や「大石りくゆかりの地」、「カバンストリート」などの見どころがあります。
元気な方は、「コウノトリの郷公園」(約5キロ)や「玄武洞公園」(約6キロ)まで足を延ばすことができます。
「豊岡まちあるきガイドマップ」は、豊岡駅舎内にある「豊岡観光案内所」で、お渡ししています。



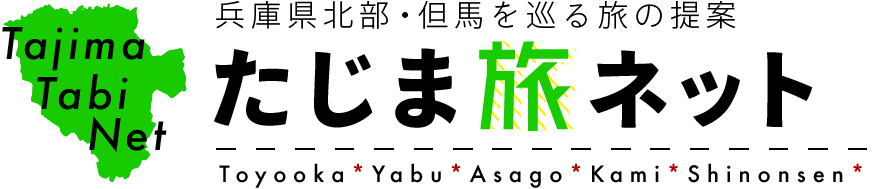







 ︎
︎





















 090-9703-9357
090-9703-9357